弱音を吐いちゃいましょうよ!
テレビに映し出された里親家庭
ある日のテレビ番組の中で、里子たちと生活を共にする里親さんの活動が紹介されていました。私たち夫婦は「こんな働きっていいよね」と話したのが、里親になるための小さな願いがともった日なのかもしれません。
数年後、夫が某児童養護施設に関わるようになったのも不思議なご縁でした。子育て経験のある年配者の協力が必要とのことでした。若くて元気な人材だけでなく、経験を経た者もお役に立てるのだなと感じました。
そうこうしているうちに「里親月間」や「里親募集」のポスターが目に留まるようになりました。私も含め多くの人が素通りする中、その時には、私たちに何か語りかけているように思えたのです。ついに、私たち夫婦は里親登録へと踏み出したのです。
最初にあずかった〝いのち〟
最初のお子さんは生後間もない赤ん坊。すでに実子を育てていたので経験はあったものの、大切な〝いのち〟をあずかっている感覚はよりひとしおでした。
大きな社会の中では、里親の仕事は小さなひとつの歯車にすぎないでしょうが、こんなちっぽけな歯車だって回さなくっちゃ世の中は動かないんだよねと、小さいながらも誇りと喜びが感じられました。
やがて、その子も実親さんのもとにお返しすることになったのですが、数年後に別の里親さん家庭で暮らすことになったようです。その間の経緯は私の知る限りではありませんが、里親同士の交流の場で再会を喜びました。その間いろいろとあったのでしょうね。でも、一番大変な思いをしているのは里子ちゃんです。
そんな彼も自分の生いたちをたどる〝ライフ・ストーリー・ワーク※1〟の中で、わが家で過ごした時の写真を見ながら少しずつ納得というか、悲しみや怒りや今の幸せもみんな含めて、その小さな心で受け留めている様子に感動をおぼえます。
ライフストーリーワークって大事なんですね。自分のルーツをたどりながら、自分を自分として受け入れて行く作業は、そのお子さんの大事な土台になるように思うのです。写真とか記録を残しておくことの大切さを実感しました。
ファミリーホーム
さて、その後、私たち夫婦はファミリーホーム※2 を開設することにしました。大きな決断でしたが、それまでの経験や感動が後押ししてくれました。
覚悟はしていたのですが、生後2 ヶ月の双子ちゃんをあずかった時は心身共に大変でした。ひとりを抱っこして授乳しながら、もうひとりのベビーベッドを片足でゆらしてあやす毎日で実感したことは、双子のお母さんやワンオペで育てているお母さんって大変だろうな~ってこと。これはもうSOS を出さないと壊れちゃいますよね。里親も同様。ですから、皆さん遠慮なくピアサポグループや児相さんにヘルプ要請しましょうね。
もちろん夫も助けてくれましたが、私は事あるごとに、子どもたちを連れて地元の児童館や里親サロンに出かけました。そこには〝子ども大好きおばさん〟たちがいて、かわりばんこにあやしてくれて、随分と助かりました。子育ての悩みをかかえ込まないで、そういった「社会資源」を利用するのはオススメです。そこで弱音を吐いたり愚痴ったりするうちに元気をもらいました。
実子と里子たち
実子と里子たちの関わりを最後にお話しておきますね。実子が小学生の頃から里子たちと暮らすようになったのですが、わりと自然に受け入れてくれたように思います。でも、ファミリーホームになって大変な様子を見て、「もうこれ以上増やさないでね」って言われたこともあります。といっても親の心労を気遣ってのことだと思います。
里子ちゃんたちは、実子のお兄ちゃんたちが里ママから生まれたことを最近になって知って驚いていました(いやこっちが驚くよと言いたいが……)。でも、それくらい家族の一員として区別なく生活できていることに感謝です。それがきっかけなのだろうか。お皿に盛られるおかずの量の微妙な違いを気にするようになったのですが、そんなちょっとしたヤキモチを愛おしく感じる今日この頃です。(里母S)
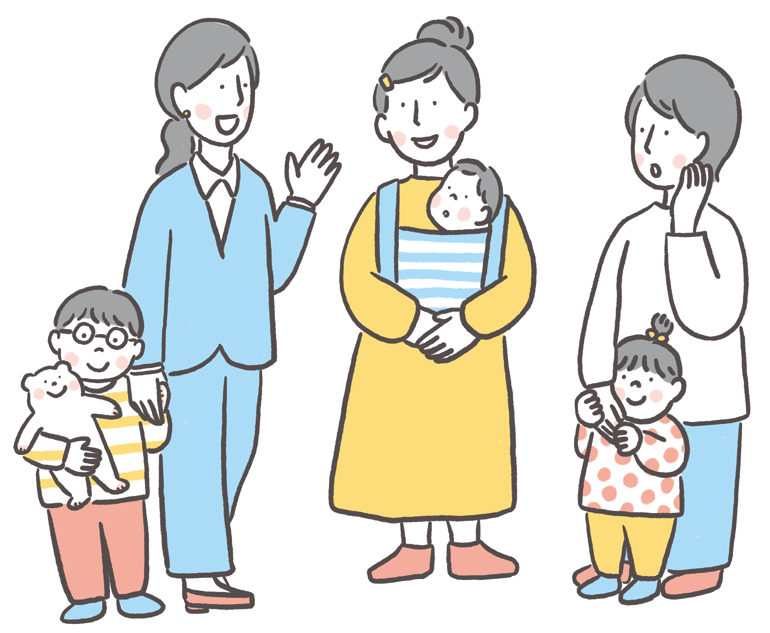

※1 ライフストーリーワーク子どもの日々の生活やさまざまな思いに光を当てて、自分は自分であって良いということを確かめる作業のこと。自身の生い立ちや家族との関係を整理し、過去・現在・未来をつないで前向きに生きていけるよう支援する取組みのこと。
育った施設や里親宅での記録を残し、それが途切れないように里子につないで行くことの大切さが提唱されている。写真はその顕著な一例といえる。

※2 ファミリーホーム小規模住居型児童養育事業のことで、「里親を少し大きくしたもの」と表現されることがある。里親の場合、養育できる子どもは最大4 人までだが、ファミリーホームの場合は6 人まで養育が可能。また、里親を助ける補助者を雇用することになっている。